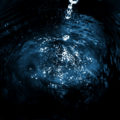田中古代子の本名は、戸籍では「コヨ」でした。1991年 田中古代子の未発表詩編を発掘編纂し詩集『暗流』を出版した中山昇治さんに拠れば「初め、「孤夜子」「田中こよ子」の名前で創作、評論、詩などを地元の同人誌に発表し、その後県下初の女性記者として米子の「山陰日日新聞」に入社したのちも筆名「孤夜子」で辛口コラムを書いている」【詩集あとがき】とあります。「田中古代子」というペンネームをいつ頃から使い始めたのかは定かではありません。ただ、あの平塚らいてふが雑誌『青踏』発刊に寄せて「元始、女性は太陽であった」と書いたのが1911年9月=コヨ14歳の秋、「新婦人協会」を設立したのが1919年11月=コヨ22歳ということを考えると、東京・中央の文芸雑誌を読み「新しい女」としての自覚と自負・共感からコヨを「古代」とし、自らを太陽になぞらえたのではなかろうか、と推察したくなります。
古代子が「太陽」だったとするなら、その光を浴びて輝いた千鳥は「月」でした。千鳥は、月からやってきた「小さな人」、月から遣わされた「かぐや姫」だったのだ、そう指摘する人がいます。評論集『千鳥 月光に顕(た)つ少女』を著した上村武男さんはこう書いています。「竹取物語のかぐや姫のように、「約束」どおり、そつちの世へ還って行ってしまった」
さらに、こうも言えそうです。
母・古代子は、あくまで今この世を生きようとした「現世」の人でした。表現者である以上に、この世この社会に何かを主張したい・伝えたいジャーナリスト=報道者「報じ道(い)うヒト」だったのではないだろうか。それに比して、娘のチドリには、「現世」この世にありながらどこかあの世を見ているはかなさが漂っています。チドリは、あの世を見る「前世」「来世」の人ではなかったか、と思えてくるのです。もっと言えば「前世・現世・来世」を超えた「永世」の人(いのち)なのだと。人事に縛られた母‥と人事を超えた何かに触れた娘‥。
うがち過ぎなのは承知です。
ただ、チドリの詩文、チドリの遺した言葉は、どれもやさしくおだやかでありながら、その奥に、するどい虚無のような寂寥が横たわっているように見えて仕方がないのです。
哀しいことに、人は長じるにつれて、上下や優劣・勝ち負けを気にかけはじめます。小さな千鳥には、上下も勝ち負けもありません。損得も計算もありません。ただ、傍にいて見るだけです。見たものを描くだけです。無心に。無欲に。彼女の言葉は決して幼く無邪気なものではありません。子供じみているわけでも大人びているわけでもありません。母古代子には、自身 物を書く表現者の一人として、その才・力量に気づき、早くから認めていたのだと思います。古代子には「自らの才を超える娘の、良きプロデューサーたらん」