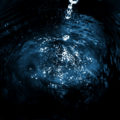彼女は小學校の二年生にまでなつてゐたが何故か、挨拶のしかたでも、歩き風でも、學校といふ所の氣風色彩―學生型―に染まらず、最後まで獨特なアブノーマルな成長をしてゐた。
私は常に考へさせられた。いつまで抱き温めてゐたら浮化する卵か? どんなひよこが生れて來る卵か? ひよつこの見當のつかないまゝに、卵ばかりが大きくなってゆくやうなので、外殻の裡にひそまってゐる不思議な雛鳥に、充分の注意を傾けて期待してゐた。
あらゆる意味で、成長困難だとは思ってゐたが、ひよつこは遂に生れずして、その不思議な華かな毛色のまゝに、文字以外の冷たさに還つてしまつたのだ! 恰も、殻を破りかけて、外光の強さに堪へられなかつたかのやうに―。
病熱に苦しむ小夜中に、蚊帳の外の淡い電燈の光りを見てさへ、「光線が強い! 光線が怖ろしい!」と傷々しく恐怖した。「光線」と云ふ事を口にする度に、激しい痙攣に襲はれた。
そして三日の間、光線の恐怖と痙攣に苦しめられ、七日の間昏睡して虚空を彷徨し、遂に黎明の星の中へ、安らかに微笑して走り去つた!
去つた彼女は幸福だ! 星のおともだちに取りまかれ、毎夜々々、地上に歎く私達の煩悩の姿に、あの清らかな涙を垂れてゐるであらう。
彼女の追慕は、この纂にはあまり書けないし、私としても後日、彼女の小さな軆に抱擁されながら落付いて書きたいと思つてゐるが、二三の斷片をこゝに記して、彼女が生前の姿を、皆さんにほゝゑんで頂きたい。
病氣づく二日程前―八月七日頃―のことである。彼女の「お父ちやん」は上京してゐて留守であつた。私は彼女に云つた。
「おとなしくしてゐると、お父ちやんのおみやがどつさりあるし、お行儀がわるいと、少ししかないよ」と。すると彼女は一寸困つた顔をして、注意深く私にたづねた。
「母ちやんは、わたしのお行儀のことを毎日お父ちやんに手紙で出すの?」
「手紙では書かないけれど、書かなくてもお父ちやんの心には、お前が毎日どんなにしてゐるか、何も彼もちやんと判つてゐるんだよ。」
「ふーむ」と彼女は、いかにも感じ入つた面持をしてゐたが、やがて「そんならお父ちやんは、よつぽど第六官が發達してゐるのだなあ!」
私は思はず失笑したが、祖母は第六官が解らないので、すぐ彼女に問ひ返した。すると彼女は大得意になつて、人間には五官しかないこと、動物には第六官があつて、何でも豫感することなどを、いつの間に小耳にはさんだものか、細々と説明して祖母を驚かした。
そして頓與に「さうすると‥‥お父ちやんは動物! おかしいなァ」と手を打つて笑ひ與じたものだつた。
「お父ちやん」の歸宅は、すでに彼女が昏睡の深淵に陥つてからで、すべて駄目だと失望してゐたが、待ち焦がれてゐた彼女は、その呼聲に、奇蹟的な答へをして、物言ひたげに唇邊を動かし微笑の影を浮かべた。
「お父ちやん」の第六官に通じたお土産の草履やリボンやロビンソンクルウソオの物語本などはうつろな瞳にうつりしや? 彼女に第六官があつたなら、これらの土産は見ずして知つてゐたであらうけれど‥‥‥。
今年の五六月頃であつたと思ふ。彼女は二學年になつてから、些少も學校の唱歌を唄はないので、私は或る日たづねた。
「この頃唱歌は教はらないの?」
「習ふけれど‥‥」と彼女はいつもの考へたやうな瞳を向けて云つた。
「厭な唱歌をならふ時は、一時間中耳の穴をふさいでゐるし、好きな唱歌の時は、ぼんやり夢のやうに聞いて、いゝ氣持になつてゐるので、おぼえられない。」と云つて、何かすまなさそうにしてゐた。
「學校の唱歌は、まつ四角な感じがして厭だ。宅の歌が一番好きだ」と云つて、私達の唄う歌は、何でも一所によく唄つた。ゴルキーの「どん底」の歌
夜でも晝でも 牢屋はくらい
いつでも鬼奴が 窓からのぞく
殊にこの歌などは氣に入つて、夜でも晝でも情緒をこめてよく歌つた。インタナショナルの歌も大分うたへ出してゐた。そして歌の意味を何處までも追究するので、説明に弱らされたものだつたが、私達の思想を或る程度まで理解してゐた。たのしかつた!
彼女は強い個性を持つていた。教育と云ふやうな一切の事は、彼女を導く何物にもならなかつた。教へたからと云つて「教はる」やうな子ではなかつた。自分の氣に入つた事だけして、自分の氣に入つたやうに生活しなければ、きかない子であつた。
「お前、大分長く机に向はないが、少しは何か書いてごらん。」
「このごろ、ちつとも氣が向きません!」
そんなふうであつた。雨の降る日が大好きで、雨の日にはころつと人間が變つて仕舞つた。居るか居ないかわからない程、ヂツとしづかにしてゐて、口も利かずに一人で何かしてゐた。彼女はかりそめにも嘘や出鱈目を云はなかつた。彼女の言葉はそのまゝ信じてよかつた。その点非常に安心してゐられた。
學校の「綴り方」の時間は、体操時間よりも嫌つてゐた。一寸は、不思議にも思へるがなかなか氣の向かない彼女には―創作的なものが好きであるだけに―學校の制限的な「綴り方」の時間が氣に入らなかつたのは當然すぎる事なのである。「先生が題をきめられるし、みんなが八釜しいし‥‥」と云つて、消氣て歸るのが、いつものやうであつた。そのくせ、宅で遊んでゐると、いろ??な機會に、素的な詩や作文が出来るのであつた。
二學年になつてからは、自修で持つてゆく作品はすべて受持女先生から疑はれてゐた。一日に二三時間、どんぐりの脊くらべのやうな中にあつて興味なく過し、たまたま自由作品を持参して疑いの眼に蔑視されてゐた様子は、彼女のために氣の毒であり實に遺憾であつた。
無論、家庭の影響はある。しかし、彼女の手を執つて物を書かせるやうな冒?は、嘗て試みもせず、彼女自身が受入れもしなかつた。一寸した添削すら彼女には氣に入らなかつたのである。しかし受持先生の疑ひも無理とは思へなくなつた。何故なら彼女の歿後、種々なノートを集めて見るに、朝夕育んだ我子ながら、驚かざるを得ないものに多々接した。今では先生の蔑視をこゝろよく認容してゐる。
彼女が何か書いた塲合に「素的だ!」と私がほめてやると彼女は「そんなに素的なら學校には持つて行かない。」と云ふのが常であつた。
今度の病氣になつた日も、何を考へてか不意に「母ちやん、夏休がすんだら、寳木の學校に行きたい、一度連れて行つて貰へば、後は一人汽車で通ふから‥‥」と云つた。
「學校なんか、もうどうでもいゝのこんど病氣が治つたら決して學校には行かなくてもいゝから、おうちで母ちやんと遊ぶんだから‥‥」と私が言ふと、大層よろこんで意識のあつた間に二度までも、「學校に行かなくていゝのが一番嬉しい、早く治つてお庭が歩きたい。」と囈言のやうに云つてゐたが、思へば、厭な顔もせず學校に通つてゐた間の、彼女にしつくりしない生活をほんとにすまなく思ふ。
二學期になつてからは、?が丈夫になるんだからと、すゝめて??やうやく体操にも加はつてゐたが、一學年の時は絶對に体操と云ふものをしなかつた。一學年當時の受持先生は、幸ひにいろ??な点に理解を持つて下すつたし体操時間にはいつでも、一人教室に残つてゐる事が出來たさうである。
そんな場合、一人で繪などを描いてゐると上級の男生徒が彼女を取り巻いて、「生意氣なチドリ、やつたれ!やつたれ!(やつけろの意)と喚き立てゝ詰めよせたさうである。彼女は笑ひながら私達に話した。
「その時わたしは(やつたれ! つて、何をやつたるの?やるものがあるなら、もらはうか、さあ、貰はうか。)と云つて手を出したら、みんなが默つてへんな顔をして逃げて行つた。」と、さも面白さうに話して私達を笑はせた。
また或る時は―今年の五六月頃―矢張り上級の男生徒が「大頭、大頭」と綽名してからかふと云つて歸つて來たので「お前の頭が大きいのではない他の子の頭が小さいのだが、お前はたつた一人斷髪だから、フサ??して大きく見えるのだ」と云つて彼女の頭を撫でた。「しかし、矢つ張り大きい方だな。」と皆で笑ひ合つて居た。すると或る日學校から歸つて面白そうに話すには「今日も男生徒が大頭々々とからかつたから、お前達は私の、この大頭の中に何が這入つてゐるか知つてゐるのか? と云つてやつたらみんなが笑つて逃げて行つた。と話したので、私達はその機智を笑ひ、ゆとりのある神經をうれしく思つたのだつた。
去年の秋、六十余日の肺炎から、やつと命を拾ひ上げて、皆がくりかへし喜んでゐる時に、彼女は淋しい面持をして歎じた。
「病氣をすると死にたくない死にたくないと思ふし病氣が治ると地震や火事が怖ろしくて、生きてゐるのが心配だしいつそ生まれて來ない方がよかつた‥‥。」
この言葉には皆が驚かされ考へさせられた。
いつたいに、あまり友達を求めず、一人で遊んでいる子だつたので私はよく「何故、お友達と仲よく遊ばないのか」とたづねた。「仲が悪いのぢやないけれど私と同じ事をして、同じ事の好きなお友達が一人もないんだもの‥‥」と、物思はしげに答へるのであつた。
かなり憂鬱で、怖ろしく?無的な考を持つ子であつたが、死の前二三ケ月は全く不思議に思はれる程の人なつこさで、誰とでもリスのやうによく遊んだ。私達は、それだけ?が丈夫になつたのだと信じて喜び合ひ乍らも彼女の健康法には神經を使ひ通してゐた。
今年は、裏庭の、あんずが「鈴なり」に實つてゐたが、彼女は毎日々々七八人づゝの友達をよんで來て、その樹の下から遊びながら熟れるのばかり待ち、待ちきれなくてもぎ取つては友達に分けてゐた。よく熟した頃には數も少なくなり、自分では幾つも食べなかつらう。
又彼女も、山の友達にはお花を、海の友達には貝殻、小石、生きた蛤小蟹を、又、不良少年で人々から?悪されてゐる少年からまでも雀の子を貰つて、編中の雀日記を書いた。小蟹を貰つてよろこんでゐたが、飼ひ方に困つてたう??遠い友達の家まで返しに走つたこともある。
お花と云つたら、他家のゴミ捨塲からでも拾つて來て、奇麗に挿し並べ、机のまわりはいつもいつもお花ばかりで埋まつてゐた。
彼女がまだ「感じ」一つで、極端な愛?を示してゐた頃から、たつた一人、夜も晝も離れたくない程好きな「お姉さん」があつたが最近は遊びに行く度に、赤ちやんの乳房を拝借してその膝に乗り美味しそうに乳汁を吸つてゐたさうである。
彼女の奇妙な癖は、何でも彼でも持物を至る所に置き忘れて來る事であつた。貸したり借りたり、やつたり貰つたり自分の所有を些も重大?しない故? かと思はれた。
お姉さんの家に、一番最後に遊びに行つた七夕の日には何も残さず持つて歸つてゐたので不思議な事だと思つてゐたと、後でその人が話して居られた。
彼女の讀書力は、最近いちじるしく進んでゐた。すべて頭腦の發達は恐ろしい程で理科の話なども、書物にあるまゝ一点違へず話す程であつた。追求し追求し説明を求めるので祖母など弱らされてゐた。
昨年の夏頃から「赤い鳥」を手にしてゐたが、今年の三月頃からすらすらと、よく讀めるやうになつて、毎月、祖母に朗讀して聞かせるのが唯一の遊びである、また得意でもあつた。對話の個所なんかは、うまく調子つけて對話らしく讀んだものだつた。「赤い鳥」が來ると、いつでも學校を休みたがつたものだ。雨の日など、私の眞似をして寢ころんで、ヂツと默讀してゐる様子には、いつもほゝえまされてゐた。
鈴木三重吉氏の「宿なし犬」を讀んで泣いた姿、江口喚氏の、「暖かい日の出來事」等に笑ひころげた姿、大人らしく批評めいた事を云つた瞳、それ等が堪らなく目に浮ぶ。
今度も、昏睡に入る前まで、「赤い鳥」を持つてゐたのに、靈魂去つた枕邊にそれが着いた時は、迚も、たまらなかつた。
イソツプ物語もよく讀んだが、ある時「蟻ときり??す」を讀んでから、すつかりイソツプに興味を失つてゐた。何故と云ふに―冬になつて食物に餓えたきり??すが、お隣りの蟻の所へ行つて、食物を少し惠んで下さいと云ふのに、蟻は、夏の中歌つたり踊つたりしてばかりゐたきりぎりすを嘲笑つて、
我々蟻は 貸しもせぬ
我々蟻は 借りもせぬ
と唄ひながら、せつせと働いてゐた―と云ふ物語りを、彼女は大層不満がつた。
「わたしは、讀みながら、蟻が親切にきりぎりすを助けてやるだらと思つてゐたのにこんなおもひやりのない話は大嫌ひだ」と云つた。
彼女は花と小鳥を中心に、濘の中のおたまじやくしに至るまで、極端に熱愛してゐた。彼女が、ありとあらゆる物に愛を傾けた悲喜様々の追憶は笑話となり愛惜となつて、限りなく甦つてくる。
あまりに繊細な感情をもつてゐた彼女は、悲劇的な或る物が素質の中に閃いてゐたので、ある年頃に至つては華かに自殺しかねない子だと、思ふ不安に襲はれる事も度々であつたが、かほどに早く執着なく、我等の濁世を去ららうとは思ひもかけなかつた。
残る者こそ嘆き悲しめ、彼女にとつては星の世界こそ、清らかな静かな、いかに心地よい安息の床であるだらう。
取り残された私達、チドリよ! 私達こそ可哀さうではないか!明日をも知らず煩惱に煩惱を量ねて生き殘るのだ。
おお星よ星よ! その蒼き光りを惜しみなく永劫に、雑草の中にゐて嘆く我等が上に!
(一九二四.八.二五)
追慕しつゝ 母