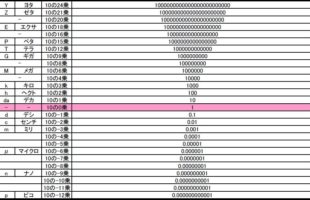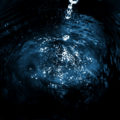知らないのに 知っている
初めてなのに 懐かしい
遠くから すぐそばで
小さくて 大きな力
チドリは古くて 新しい
このブログでは、田中千鳥の詩の世界に触発されて生まれた様々な声・言葉を発信していきます。
上村評論「千鳥 月光に顕(た)つ少女」分載 その2
2
こんな手紙がある。死ぬ二週間ばかり前のものである。
「私はげんきで、まいにち朝はやく、お星さまの出たくらいのうちに、おばあちやんと朝日をおがみに海に出ます。お日さまがでるまで、海の中に、はいつて水をあびます。
はじめには、なみのこないところでも、よういきませなんだが、ふかいところまでもはいつてゆくやうになりました。
すて犬をつれて、うみまでゆき、犬はかへるまでまちてゐて、かへる時にもついてかへりました。
まつ赤な、朝日が空一めんに、こうせんをひろげ、きれいな海には、朝日がうつり、山にはかすみがかゝり、水と空がどっちがどつちだが、わからないやうになり、白浜が見へ四方八方がきれいです。
それをおぢちやんに、ゑにかいてもらつたら、どんなに、りつぱに、かけるだろうと、おもひました。さようなら。 八月二日 チドリ おぢちやん」(大正13年)
おじちゃん(母親の弟)は絵を描く人だったのであろうか。その大阪在住の叔父に、早暁の海辺のようすを伝えようとしている手紙。千鳥は七歳。これも先の詩と同じように、さっと読んでしまえば、なんでもない、単純素朴な便りのように思える。けれどもこれ――にかぎらず千鳥の言葉のすべて――は、そんなに速読しないで、ゆっくりゆっくり読むべきものだ。あたかも、小学低学年の子が、習い覚えた字を一字一字、刻みつけるようにかきつける、そのスピードで。そして、その息づかいで。
母親が、註記を書き添えている――《この手紙を書く前に、祖母が「毎朝海に出ることを〔書いて〕出しなさい」と注意しかけると、彼女は向つてゐた机の前を飛び離れて「おばあちやんが言つて仕舞ひなさるならわたしは書かない。せつかく私が考へてるのに……」と大層怒つて躯をゆすぶつた。祖母はあはてゝ詫びを入れたのであつた。そして、愉快げに手紙を書き書き、彼女は書きたいことがあんまり多くて、原稿用紙一枚が足りないけれど、今日はこれで仕舞つて置かうと云つて「朝の月」の詩をそへて出した》と。
その時の情景が、目に見えるようだ。「朝の月」は、つぎの詩である。
まだよのあけぬ
白月よ
お星のおともを一人つれ
お月様はどこへゆく
朝日をおがんでかへりがけ
ちらりと空を見上げたら
お月様は しらぬまに
お星と いつしよにきへてゐた
月のゆくへは わからない (大正13年8月1日、朝)
この詩をわたしはこのあいだ、兵庫県阪神シニアカレッジというところの「自分史」講座で朗読をした。そして、ゆつくりとした口調で読んでいき、最後の二行目から一行目に移る間合いに、ちょっと声がつまって落涙しそうになった。自分でもなぜだかわけが分からない。宝塚で開かれるその講座はもう三年続けているが、こんな体験ははじめてだった。
「月のゆくえはわからない、か」
と思ったとたん、わたしは胸の思いがあふれた。千鳥の歳からは五十年も生き延びたわたしであるのに、見知らぬ七歳の女の子に、月のゆくえはわからないといわれてしまえば、わたしの側に、それに備えるべき、なんの準備があるだろうか。