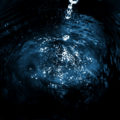【 ⇑ 今回のアイキャッチ画像は、黒田清輝の油彩『案山子』1920(T9)】
これまでは大正という時代と社会を外側から鳥瞰的に見てきましたが、ここで百八十度 視点を変え、田中千鳥という一人の少女が鳥取の浜辺の村で実際に見たもの、眺めたであろう風景・目にしたものや暮らしぶり、彼女の生きた半径数十メートルか多くて数百メートルの世界を、出来るだけ描写して行きたいと思います。(もとより、勝手な妄想以上ではありませんが)出来る限り大正時代の一人の少女の眼になって見たもの・見えたものを、視覚だけでなく五感丸ごとを使って感じたであろうことどもを、さらにその空気・気配までを描き出してみよう、との試みです。
手始めに、彼女が書き残した「作文」と「日記」に書かれたモノやコトを手掛かりに、手探りで漕ぎ出してみます。母・古代子が編んだ『千鳥遺稿』には、「自由詩」に続いて、「作文」として「カガシ」(七歳)六月、「ニイチャンノオハカ」(七歳)七月十一日、「すなにうづめた雪」(八歳)二月「かわいいすゞめ」(八歳)三月「風」(八歳)六月「雨のやんだ ばんかた」(八歳)五月「ほたるとり」(八歳)七月 と七つの作文が載っています。そこには、バシャ、オミヤ、タンボ、カガシ、オハカ、はま、すな、雪、スケッチ、すゞめ、江さ、畠、まめ、風、よしやぶ(葭薮)、あめ、せり、かへる、夕日、ほたる、月よ、つゆ、などが登場しています。
1917年 春から夏にかけての或る時期、夫婦仲が毀れた母・古代子は、生後間もない千鳥を連れて、米子から気高町浜村・勝見の実家に戻ります。以来、亡くなるまでの七年余り勝見の実家で千鳥を育てます。実家は、山陰線開通後、浜村駅前に日本通運公認運送店を営む裕福な暮らし向きだったようです。ハイカラモダンな様子が浮かびますが、水道はまだ敷かれず井戸水か湧き水、やっと裕福な家庭や商家中心に電気電燈が普及し始めた頃のことです。それまでの灯りは、ランプやロウソクでした。千鳥が生きた日常は、まだまだ自然や四季の変化とともにあったことがうかがわれます。人工物に囲まれた今となっては、想像も及びにくくなりましたが、作文からは、自然との距離の近さが伝わってきます。
作文の中で目を引いたのは、「スケッチ」ということばです。幼い千鳥が「sketch」という英語を知っていたのかと不思議に思い、ちょっと調べてみました。Wikipediaの「写生」にはこうありました。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%99%E7%94%9F 明治時代になると西洋絵画の訳語として〈スケッチ⇔写生〉という語が当てられ、大正時代には「学童を手本の模写から解放し、直接自然に親しませるための自由画教育が普及、それに伴って、事物を実際に見ながら書いたり、戸外に出て風景を写しとったりする「写生」が図画教育に盛んに取り入れられることとなった」という記述を見つけました。さらに「江戸時代の画論における「写生」は概ね4つの意味が渾然となったまま用いられていた。すなわち、生意(生きた感じ、生気)を把握し描写すること(「生意写生」)、客観的正確さを主眼として描くこと(「客観写生」)、精巧・細密な描写を行うこと(「精密写生」)、対象の観察と同時に描いていくこと(「対看写生」)である。」ともありました。とするなら、千鳥は「事物を実際に見ながら描く」写生=スケッチを知っていて、その写生は、「生意写生」であり「対看写生」であったということになります。千鳥のことばが、まっすぐ事物に向かい、平明でありながら丸ごとを捉えた深さを感じさせるのは、この「対看」「生意」という姿勢=手法にあったのだ、と言いたくなりました。