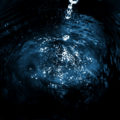知らないのに 知っている
初めてなのに 懐かしい
遠くから すぐそばで
小さくて 大きな力
チドリは古くて 新しい
このブログでは、田中千鳥の詩の世界に触発されて生まれた様々な声・言葉を発信していきます。
なれそめとなった上村武男さんの評論は、のちの単行本として出版されました。上村さんの許諾を得て、5回に分けて掲載していきます。【編集工房ノア 2002年6月15日初版】
1
わたしは、幼い子供の詩や文章を読むのが好きだ。子供たちに向かつて語りかけ、何か、詩や絵本や紙芝居や物語などを読んだりすることもきらいではない。
先日、母校の小学校から依頼されて、いそいそと出かけて行き、三年生全員(といって八十人ぐらい)を相手に、いまはむかしとなった故地の自然や学校のことなどを九十分も「授業」してきた。大へんに愉快であった。
そんなわたしが、こんど、思わぬ一人の少女と出会った。名前を田中千鳥という。
この秋(平成十二年)、わたしは父の小学時代の日記を『大正の小さな日記帳から』という本に編んで出版したのだが、その直後に、ある縁で、山陰鳥取の気高町浜村という海辺に近い村で大正時代に生まれて、たちまち死んだ少女のことを知った。それが田中千鳥である。千鳥の一生は、わずか七年半で、あまりに短かった。大正六年二月に生まれて大正十三年八月に死んだのだという。死んだとき小学二年生であった。
母親が『千鳥遺稿』と名付けた小冊子を、娘の死後まもなくに作っている。わたしはそれの平成十年の復刻版(気高町教育委員会・文化協会刊、非売品)を、人に借りて読んだ。そして、ふしぎな感銘に浸された。
わたしの父の日記は大正十年から十三年、小学三年から六年にかけてのもの。ところが『千鳥遺稿』のほうは、その父の日記がはじまる小学三年よりもさらに以前の、満六歳や七歳という時点の「作品」――詩と日記と作文と手紙だった。そしてそれは父の小学生日記が綴られたのと同時代で、しかも自分が〈わが魂の幻境〉として久しく親しんでいる山陰の地の少女の手になるものであった。
こうした事情が、わたしを感慨に誘ったのかもしれない。
しかし、千鳥は詩を書く少女で、その千鳥の詩は、読めぼ読むほど、余白が広い。それは、幼くて、言い足りないところがたくさんあるという意味ではない。
無限のように余白が広い。それは、いいかえれば、とつぜん堕ち込んだような余韻の深さだ。
わたしは『遺稿』を読むにつれて、胸が高鳴った。そして、しぼしば天を仰いで感嘆するほかなかった。
ナ ミ
ビヨウキノアサ
ハヤク メガサメテミレバ
ナミノオトガ
シヅカニシヅカニ
キコエテクル (大正12年7月、6歳)
なんでもない詩だ。が、なんという広漠とした余韻だろう。そして深い余韻だろうと思ってわたしはこれを読む。
けむり
ばんかたの空に
ぽつぽつと
きへてゆく
きしやのけむり (大正13年8月8日、7歳)
これが絶筆――最後の詩だという。『千鳥遺稿』に添えられた母親の「編纂後記」によれば、千鳥はふだんから病弱だったが、急に高熱を出してなくなったようだ。たぶん、肺炎のような症状だったのであろう。
千鳥が書いた最初の詩として遺っているのは――〈キノハノ オチタ/カキノキニ/オツキサマガ/ナリマシタ〉(大正11年11月、5歳)という。初冬の夜、すっかり葉を落とした柿の木の枝に、黄色い柿の実がなるように、登ってきたお月さまが、ちょうどいま、実っているよというのだ。