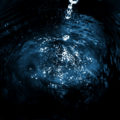田中千鳥は何度か新聞記事に取り上げられ紹介されてきました。そんなときには「天才少女詩人」といった見出しが使われます。わずか七歳半で夭折した知られざる天才少女詩人を発見!といった具合です。読者の注目を惹くために刺激が必要なのは認めますが、「天才」とか「才能」とかの言葉にはいささか違和感を覚えてきました。そう思っていたら先日、最果タヒさんという詩人のこんな文章に出会いました。
「人はどうして「才能」なんて言葉を使うのだろう、と思う。才能という独立したものはないし、便宜上才能と呼ぶしかないものもあるが、‥」(エッセイ集『神様の友達の友達の友達はぼく』【2021.11.30 筑摩書房 刊】所収「空が青いですね」より引用:)

途方に暮れるほど深く強く心を動かされた感動に出会ったとき、それが何故なのか、その中身がわからなくて才能という言葉を使うのだろう、と最果さんは書きます。
「‥なかの分からなさを「才能」と呼ぶことで、決着をつけられたと錯覚する。私は、才能なんてこの世にないと思うほうが美しく見えるもの、美しく聞こえるもの、当たり前のように増えると思います。実際には才能もどこかにあるかもしれず、しかしそれが孤立して人から逸れてあるわけではないし、そこに対する物語性が苦手なのでしょう。人は他者と向かい合うとき、相手も人である、ということに戸惑って、それなのに「同じ」でないことに混乱する。そうしてだから「好き」になるのだと思うのですが、近づく話に「好き」が転化していくのは不思議ですね。遠いからこそ「好き」なのに。」
彼女自身のTwitterにはこんな投稿もあります。
「才能云々の話が好きだったのは17歳ぐらいまででそれからはこういう類の話には「うるせえな空は才能で青いのかよ」と思うようになった。」
七歳半の少女に「天才」「才能」という言葉はふさわしくない気がします。「才能」という言葉でカッコに括り、片付けてしまうのではなく、もっと自然にもっと精妙な何かに魅せられて言葉が生まれ、その言葉が時空を超えて私たちに届き、それを読む私を震わせているのだと思います。