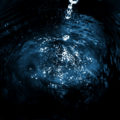知らないのに 知っている
初めてなのに 懐かしい
遠くから すぐそばで
小さくて 大きな力
チドリは古くて 新しい
このブログでは、田中千鳥の詩の世界に触発されて生まれた様々な声・言葉を発信していきます。
上村評論「千鳥 月光に顕(た)つ少女」分載 その3
3
千鳥は雨が、殊のほか好きだったという。《雨の降る日が大好きで、雨の日にはころりと人間が変つて仕舞つた。いるかいないかわからない程、ヂツとしづかにしてゐて、口も利かずに一人で何かしてゐた》と、母親が述べている。
雨の詩がいくつかある。
こぼれるやうな
雨がふる
木のは と雨が
なんだかはなしを
するやうだ
山もたんぼも雨ばかり
びつしよりぬれて
うれしさう (「雨と木のは」大正13年4月、7歳)
雨のふる日に とんできた
かわいいかわいい子雀は
おにはで ゑさを さがしてる
ぬれた雀に ゑさやれば
雀は ぱつと
かげもなくとぶ (「雨の日」大正13年6月、7歳)
わたしの父も満九歳のとき(大正十年)に、《外に出たれば雀君/「チュン」となきながら、とんで行く/其のすがたを見送れば/涼しい風がそよそよと/ほゝにあたって気持ちよい/心のそこまで気持ちよい》――などという詩を、日記のなかに書きつけているが、これは、雨の日ではなく、よく晴れた冬の日の詩。ふつう、子供は雨の日はきらいなものである。
ところで、わたしの関心を強く引く事柄がひとつある。それは、千鳥は詩や作文を、通っている小学校の担任教師に見せても、それが千鳥自作のものだとは、容易に信じてもらえなかったという一事である。
母親の述懐を聞いてみる――《学校の「綴り方」の時間は、体操時間よりも嫌つてゐた。一寸は、不思議にも思へるが、なかなか気の向かない彼女には――創作的なものが好きであるだけに――学校の制限的な「綴り方」の時間が気に入らなかつたのは当然すぎる事なのである。
「先生が題をきめられるし、みんなが八釜しいし……」と云つて、消気て帰るのが、いつものやうであつた。そのくせ、宅で遊んでゐると、いろいろな機会に、素的な詩や作文が出来るのであつた。二学年になつてからは、自修で持つてゆく作品はすべて受持女先生から疑はれてゐた》。――さもありなん、とわたしは思う。
千鳥の持つていた文章のちからと感受性のかたちとには、容易ならざるものがあるからだ。けれども、ここに述べられている学校における「綴り方」(作文)授業の事情というものは、山陰の片田舎だからというわけでは、まったくない。山陰という地には、むしろ、「綴り方」教育の豊かな、優れた伝統と実績が、大正期から昭和以降にいたるまで、息づいているのである。芦田恵之助(丹波)、峰地光重(伯耆)、東井義雄(但馬)、小西健二郎(丹波)、稲村健一(因幡)……等々の教師とその教え子たち。ただ、千鳥が出会った担任教師が、わるかったのだ。いうならば、相い性がわるかったのであろう。
題を与えて児童生徒に書かせるという課題主義の綴り方(作文)授業のやり方は、いまでもなされているが、思うに、これは教師が、いちばん楽なのである。そして、そのぶん、児童生徒は「消気て」しまうのである。千鳥がそうであったように。そして世の多くの児童生徒が、それがために文章を書くこと自体が、きらいになったように。
けれども、大正後期以降のわが国における綴り方(作文)「教育の水準は、けっして低いものではなかった。それはわたしの父の日記や綴り方にも当てはめて考えてみることができるだろう。
千鳥の場合は、不幸であった。そのことが、千鳥の作品を、逆説的に、水位の高いところへ追い上げたといってよい。