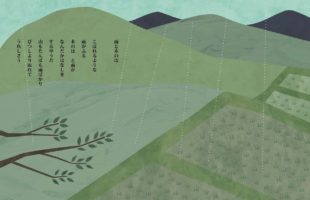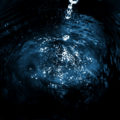知らないのに 知っている
初めてなのに 懐かしい
遠くから すぐそばで
小さくて 大きな力
チドリは古くて 新しい
このブログでは、田中千鳥の詩の世界に触発されて生まれた様々な声・言葉を発信していきます。
上村評論「千鳥 月光に顕(た)つ少女」分載 その5
5
わたしはこれまで千鳥の母親の手記を多く引用した。この母親は涌島古代子といって、ややマイナーな作家であった。
「ふるさと文学館」(ぎようせい・平成7)の鳥取県の巻に、《気高町生まれ。大正初期、県下初の女性記者や断髪で注目を浴びる。十年には「諦観」が、「大阪朝日新聞」懸賞小説に二等当選となり、各紙に小説を連載して気を吐く。しかし、胸の病いに加えて神経痛や不眠症を併発、次第に文学から遠ざかり、帰郷まもなく自宅で睡眠薬自殺を遂げた》と、短く紹介されている。
『千鳥遺稿』を編んだのほ、二十六、七歳のころということになる。
生年は明治三十年で、同じ山陰因幡の岩美出身の作家尾崎翠と、ほぼ等しい。
尾崎翠は『第七官界彷徨』という、まことに奇妙な味の、神経的な作品を書いたが、精神を病んで帰郷、その後は作品をほとんど書かず、精神病院や老人ホームに入退院をくりかえし、昭和四十六年に七十五歳で死んだ。「このまま死ぬんだったら、むごいものだねえ」と、呟いて逝ったといわれている。
先に名を挙げた金子みすゞについては、もう十年以上も前に『山陰を旅する人たち』のなかで述べたことがあるが、昭和五年に二十六歳で自殺した。
これらの人は、皆、才あるゆえにというべきか、この世にうまく棲むことが、むつかしいのであったし、皆ことごとく、それぞれに淋しい命運の女性であったといわなければならない。
千鳥の母親古代子は、『千鳥遺稿』の「編纂後記」の最後に、つぎのように記している。
《あまりに繊細な感情を持つて居り、早くも厭世観をもつてゐた彼女は、悲劇的な或る物が素質の中に閃いてゐたので、ある年頃に至つては華やかに自殺しかねない子だと思ふ不安に襲はれる事も度々であつたが、かほどに早く執着なく、我等の濁世を去らうとは思ひもかけなかつた。
チドリよ! 私達こそ可哀さうではないか! 明日をも知らず煩悩に煩悩を重ねて生き残るのだ》
六歳や七歳の子供のもつ「厭世観」とは、どんなものだろうか。千鳥は、六歳の秋、肺炎で二か月ほど寝込み、その病床からようやく起てるようになったとき、家族や周囲の者がよかった、よかつたとよろこぶなか、
「病気をすると死にたくない死にたくないと思うし、病気が治るとこんどは地震や火事が怖ろしくて生きているのが心配だし、いっそ生まれて来なければよかった……」
と、淋しい面持で嘆じたという。
《かなり憂鬱で、怖ろしく虚無的な考えをもつ子であつた》とも、母親は述べている。
だいたいの想像はつく。そして、生の岸辺の詩人とわたしがいう金子みすゞの幼年期も、あるいはこれに似ていたかもしれない。
母親が娘千鳥の早世に遇って綴った「編纂後記」は、すぐれた一文であるが、それは母親その人の死をも、どこか暗示している。
山陰の魂が呼ぶ。
ほう、ほう、と呼ぶ。
と、かつてわたしは述べたことがある。
いま、千鳥が呼んでいる。