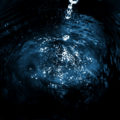作者と読者、書き手と読み手、いったいどちらが大切なのでしょうか。もとより、書かれなければ何も生まれません。けれど、読まれなければ何も始まりません。ゼロと同じです。ということで、今日は、「書き手≦読み手」論その1です。
メディアは進化しました。書き手とその普及手段は格段に拡がりました。書き手が増えたことを喜ばしいことです。表現物の大量生産・大量消費の時代。ただ、膨大な海の中で、見いだされる困難は膨らみ、忘れ去られるスピードは速まりました。こんな時代になったからこそ、今はむしろ、作り手(書き手)の精進・努力より、読み手の力能・感受(受感)こそがより重要になって来たんじゃないか、そんな思いに駆られます。書き手も大切ですが、それ以上に読み手の多様・多彩が大事、問われているのだと思うのです。根拠は幾つも浮かびます。「選ぶのは受け手だし」「答えは一つじゃないし」「どう読もうと読み手の勝手」「読者の読みは作者の意図から自由であってよい」‥‥
永らく大阪の女子大で芭蕉を講読してきた近世文学者上野洋三先生は、『芭蕉の表現』【岩波現代文庫2005年11月刊】に こう書いています。 「スゴイ文章だなァ、こう読めてよかったなァ、と目の前の学生たちとハイタッチして講義終了」これが講読授業の理想形。別のところにはこんな記述も。「読者を動かす力の基点、それを説明しないことには始まらない。‥中略‥「構成」や「構造」を考えるとき、資料たるテキストを子細に読み返す。自分の論が空想的とか幻影ではないかとか、まず疑ってかかる際に、てっとりばやい手段は、テキストそれ自体の中に、実は自分が言いたいことが、既に最初から書かれているのではないか、こちらが慌(あわただ)しく扱うので、現に書いてあることが見えないのではないか、と反省してみることである。自分自身を含めて、史料(資料)というほとんどこの世に一点しか存在しないものを理解するには、読書百遍、単純に繰り返し、繰り返し眺める他はない。「自分で考える」ほかないのだ。ひとさまの翻刻などあてにできない、エラい人の翻刻ほどあぶない。」いたく同意します。折角残された千鳥のことば。無心に、虚心に、静かに深く、向き合い続けたいものです。
「スゴイ文章だなァ、こう読めてよかったなァ、と目の前の学生たちとハイタッチして講義終了」これが講読授業の理想形。別のところにはこんな記述も。「読者を動かす力の基点、それを説明しないことには始まらない。‥中略‥「構成」や「構造」を考えるとき、資料たるテキストを子細に読み返す。自分の論が空想的とか幻影ではないかとか、まず疑ってかかる際に、てっとりばやい手段は、テキストそれ自体の中に、実は自分が言いたいことが、既に最初から書かれているのではないか、こちらが慌(あわただ)しく扱うので、現に書いてあることが見えないのではないか、と反省してみることである。自分自身を含めて、史料(資料)というほとんどこの世に一点しか存在しないものを理解するには、読書百遍、単純に繰り返し、繰り返し眺める他はない。「自分で考える」ほかないのだ。ひとさまの翻刻などあてにできない、エラい人の翻刻ほどあぶない。」いたく同意します。折角残された千鳥のことば。無心に、虚心に、静かに深く、向き合い続けたいものです。