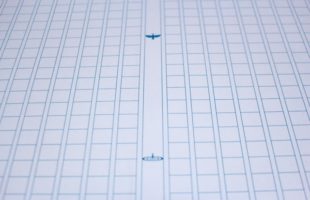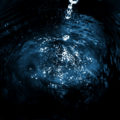今回は、いつにも増して大げさなことを書きます。
田中千鳥は七歳半で亡くなったのですから、社会も国家も民族も知りません。身の回りの家族と「家」の内外、僅かな地域の中を生きました。病弱ゆえ遠出もせず、尋常小学校と多くはない友だちとの交情のほかは、当時広まりつつあった児童雑誌などの読み物だけが経験であり知識であり、情報メディアでした。ラジオ放送が始まったのは亡くなった一年後でした。映画はありましたが、見たことがあったかどうかは分かりません。しかし、周りの自然、月や星を詠んだ千鳥の詩からは、遥かな時間と空間の宇宙的広がりを感じます。それは、家や父母、故郷といったたぐいの普段から親しい〈懐かしさ〉とは異なる、もっと突き抜けた見知らぬ〈懐かしさ〉です。人類古代からの悠久の〈懐かしさ〉というか、人が生きることの根っこにある〈寂しさ〉というか、そんな根源的な孤独・寂寥感を感じます。
「家」という身近で有り難い「揺籃・扶養器」に十全に守られながらも、それだけでは癒されない・満たされない気配が漂います。千鳥は幼くして、家や家族の持つ両義性=どうしようもない「やっかいさ」「遣る瀬無さ」を感知していたようです。法や制度・ルール・規範・社会通念に出会う以前に「ヒトは一人で生きるものだ」という自覚を感じます。既にしてすぐれた表現者としての構え=自律・自立、資質を身に着けていたのだと思います。
同時代に活動した詩人、萩原朔太郎は「人が家の中に住んでいるのは地上の悲しい風景である」と書いています。【詩集『宿命』の中の短詩「家」】尾形亀之助は、「何らの自己の、地上の権利を持たぬ私は、第一に全くの住所不定へ、それからその次へ」と書きました。【詩集『障子のある家』自序】 芥川龍之介が「ぼんやりした不安」という言葉を残して自殺したのは千鳥の死の三年後でした。
時代の中にあって、時代の空気・気分を感受しながら、時代を超えた悠久・普遍に触れる、千鳥はそんな表現者の系譜に繋がる少女のひとりでした。