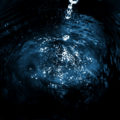当たり前のことですが、赤ん坊にとって母親は絶対、唯一無二の存在です。「三歳児神話」という言葉を聞いたことがありませんか?「子供にとっては三歳ごろまでの脳の成長が最重要。だから、その間は母親が専念するのが望ましい」という説です。これについては、専門家の間でも賛否両論、意見は分かれています。ただ、この世に生まれ一番初めの時期に一番近く深く子供に接する大人が「母親」であることは殆どの場合当てはまりそうです。
育児書には、相手の目を見て話す、出来るだけ言葉を掛ける、見られたら見つめ返す、声を出すのを聞いたら返事をする、笑ったら笑い返す、そんな積み重ねが子供を「ここに居てもいいのだ、この中で生きて行こう」という肯定感情を育てると書かれています。
そのことからすれば、母古代子は、模範的でした。彼女は、鳥取県初の女性新聞記者になるなど、大正時代当時のいわゆる「新しい女性」の一人でしたが、家庭や家族をないがしろに飛び回るイマドキイメージの「個我の強い」女性だったわけではありませんでした。家や家族を大切にする「古風な面」を併せ持った「悩める」女性の一人でした。千鳥が没する大正13年(1924年)1月発行の鳥取の文芸同人誌「水脈」に載せた「二種の夢と私の存在」に彼女はこう記しています。
私は女だ、家庭に於ける人の妻であり、幼児の母であり、また老母には一人の娘であり、一人の弟には一人の姉である。けれども人妻に即せず、母親たるに傾かず、尚又娘であり姉であるに限られない所に、それ以上の所に、私は自分の存在の価値を知りたいのだ。
身もだえしながら、裸心で体当たりしていく古代子の日常、その肉声が聞こえてくるような文章です。 この母にしてこの子あり、です。