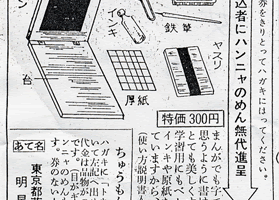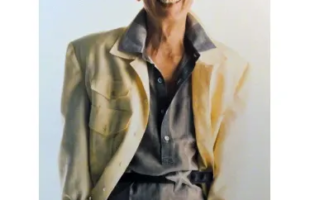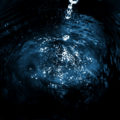千鳥や古代子が生きた「大正」という時代は、はるか昔になりました。時代・社会は全く様変わりしました。かつての「必修科目」だった映画も文学も、今は隅っこにかろうじて引っ掛かっている「目立たぬ選択科目」です。もはや純文学は死語です。「現代詩を読む人は自分でも書く詩人たちに限られてしまった」という嘆きも聞こえます。「最近上手い人は増えたが、耳に残らない」「深い所で感情を揺さぶられることが減った」そんな声も届きます。
令和という時代は何処に向かっているのでしょうか。エラソーな予言はとても出来ませんが、「過去を大切にしないものに未来はない」そうは云えそうです。大正時代がひとつの「踊り場」で、「平成」がそれまで右肩上がりで伸びてきた時代=昭和の終(末)点ではないか、そんな思いに駆られます。それが限界に届いた「到達点」なのか、単なる「通過点」なのかは分かりません。ただ、これから向かう時代・歴史への「折り返し点」になるのではないか、そんな予感がぼんやりと浮かびます。
令和二年(2020年)も「田中千鳥」が綴った言葉の世界に向き合い続けます。「加工された情報」としてではなく、いつまでも瑞々しい「眼前の生もの」として。