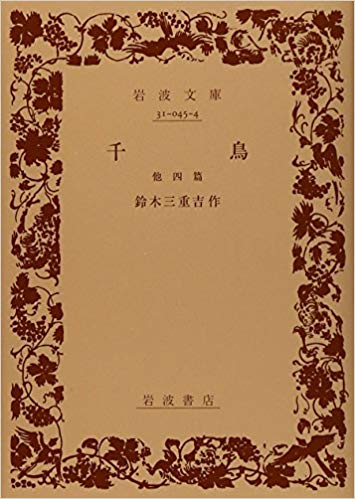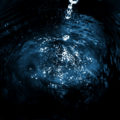散文の世界にも「千鳥」はこれまで幾つも登場してきました。近代の小説家・児童文学者 鈴木三重吉は、文字通り『千鳥』と題した小説を書いています。(このことは、以前=2019年9月1日に 一度書きました。鈴木三重吉『赤い鳥』と「千鳥」
小さな島に逗留した青年と、若い娘のほのかに淡い交情を描いたものです。三重吉の実体験としても読めるし、青年の幻想とも読める不思議な味わい、文庫本にして五十頁ほどの短編です。「さわり」の場面を引いてみます。
ある西の国の小島の宿りにて、名を藤さんという若い女に会った。女は水よりも淡き二日の語らいに、片袖を形見に残して知らぬ間にいなくなってしまった。去ってどうしたのか分らぬ。それでたくさんである。
ふと机の抽斗を開けてみると、中から思わぬ物が出てきた。緋の紋羽二重に紅絹裏のついた、一尺八寸の襦袢の片袖が、八つに畳んで抽斗の奥に突っ込んであった。もとより始めは奇怪なことだと合点が行かなかった。別に証拠といってはないのだから、それが、藤さんがひそかに自分に残した形見であるとは容易に信じられるわけもない。‥‥(中略)‥‥ しかしほかのものがどう間違ったってこんな物を自分の抽斗へ入れこむわけがない。藤さんのしたことに極っている。そうすればただうっかり無意味で入れたのではない。心あって自分にくれたのである。そう推定したってむりとは言えまい。自分は袖を翳して何だかほろりとなった。
しかし自分は藤さんについてはついにこれだけしか知らないのである。ああして不意に帰ったのはどういう訳であったのか、それさえとうと聞かないずくであった。その後どこにどうしているのか、それも知らない。何にも知らない。‥‥(中略)‥‥藤さんは現在どこでどうしていてもかまわぬ。自分の藤さんは袂の中の藤さんである。藤さんはいつでもありありとこの中に見ることができる。
千鳥千鳥とよくいうのは、その紋羽二重の紋柄である。
題名の「千鳥」は、藤さんが残した「襦袢の片袖の紋柄」にちなんで付けられたようです。
芥川龍之介の小説「海のほとり 」には、千鳥の足跡が、同じく「大川の水 」には鳴き声を聞く場面が描かれています。川端康成にも、創作ノートが鞄ごと盗難にあったために、未完に終わったとされる小説『波千鳥』があります。 他にも、長田幹彦や上林暁などが小説を書き残しました。
詩歌にしろ、散文にしろ、「千鳥」という言葉の響きから導かれるイメージは〈はかなく〉〈かそけく〉〈おぼろ〉です。くっきりではなく〈ぼんやり〉、強さではなく〈弱さ〉。いつもトワイライトの中にあり、例外なく〈影の薄さ〉が漂います。進んで前に出るのではなく、ひっそりと佇んで消え入るかのような風情です。固有の個を願うのでなく、名を持とうとしない清廉・無名を感じます。それは、どこかで作家としての自覚・自立以前に消えた「田中千鳥」を象徴しているような気がしてきます。