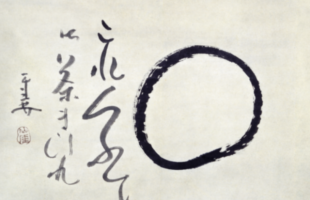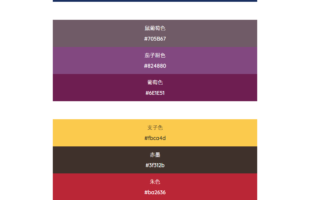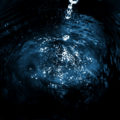『千鳥遺稿』の「編纂後記」に、こんな場面があります。上京して留守の「お父ちやん」(註:義父 涌島義博)を待ちわびる母古代子と娘チドリの会話。母「お行儀良くしているとおみや(註:おみやげ)がどっさりあるし、悪いと少ししかないよ」娘「ふーむ‥‥。そんならお父ちやんは、よつほど第六官が發達してゐるのだなあ!」
私(古代子)は思はず失笑したが、祖母は第六官が解らないので、すぐ彼女(チドリ)に問ひ返した。すると彼女は大得意になつて、人間には五官しかないこと、動物には第六官があつて何でも豫感することなどを、いつの間に小耳にはさんだものか、細々と説明して祖母を驚かした。そして、頓興に「さうすると‥‥お父ちやんは動物! おかしいなァ」と手を打つて笑い興じたものだつた。
第六官とは、今では第六感と記されることが多くなっていますが、言うまでもなく「五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)を超える直感、霊感、超感覚的知覚(ESP)や予知能力などを指す」言葉です。英語ではsixth sense:理屈では説明しがたいが、鋭くものごとの本質を予知する技能だと説明されてきました。
もとより、母娘のやりとりをもとに、チドリが霊感に優れた霊能者としての片鱗を持っていたと主張したいわけではありません。ただ、ユーモアに富んだ会話に長けた利発な子供であったことは伝わってきます。目や耳をはじめ五官に優れ,第六感で小さきもの微かなものを全身全霊で感じとり、コトバに表す力を備えていたことは間違いありません。きっとイマココを十全に生きた稀有な少女だったのでしょう。